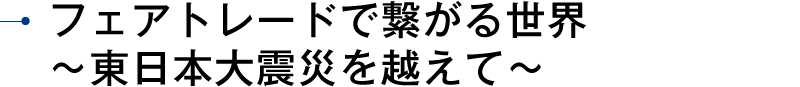ホアイフン・タイ村(ラオス)の女性が作る布がより多く売れることにより
・天候に左右されない、安定した収入源となる
・女性の収入が増え地位が上がり、生活が安定する
・家庭全体の収入が増え、子どもたちが家のお手伝いを軽減し、学校に通う時間を増やしてあげることができる
・継続的に支援することで将来的には都市との収入の格差が縮まることで出稼ぎをやる若者が減り、
村のコミュニティが保たれることが見込める
見本となる商品と作り方を得ることで、日本の高い技術力を身につけられる。
宮城県にある南三陸ミシン工房でラオスの布を使った商品を作ることにより…
・ラオスからの震災支援にお礼をすることができる
・支援を受ける側から、支援を行う側になることで、自尊心が高まり前向きな気持ちを持てる
将来的にはラオスの村人が技術を学ぶために日本に来訪し、異文化交流の期待も持てる。
期待される効果
商品を様々な場所で販売することにより
・よりたくさんの人が物品を通じて被災地に触れることで、風化を妨げる
・ラオス農村部の現状を通して、貧困やなどの社会問題を周知でき、関心が深まる
・フェアトレード(国際協力)が身近なものになる
(※日本は現在、フェアトレード国の中で最下位。フェアトレードの意味を知っている消費者の約6%)
・南三陸町とホアイフンタイ村を知ってもらうことで、行くきっかけになり観光面でのサポートに繋がる
拓殖大学の学生にしかできない企画
・拓殖大学を代表して、JICA職員として2人の学生がラオスで活動したことでできた繋がりを
拓大生が持つチームワークを生かし、他の学生が体験を共有し発展させることで、代表者だけの活動で終わらない
・今後もJICA隊員としての派遣があるため、コネクトできる地域は増えていき、活動の幅が広がる
・6つのコースを持つ国際学部、各地域言語の愛好会や研究会、運営を学ぶ経営学部、
もの作りの工学部など、拓殖大学の広い学びという長所を生かした活動により、大学全体に大きな流れが生まれる
国と国との仲介役の実践により、大学の理念であるグローバルな人材が育成される。
![]()
学チャレプレゼン前
企画の流れを決める
途上国・被災地の取引可能な相手のリストアップ
→途上国:ラオス ホアイフン村 カトゥ族の女性
被災地:宮城県 南三陸町 南三陸ミシン工房 被災されたお母さん方
![]()
学生チャレンジの合格発表後
6月~
フェアトレードの勉強会
フェアトレードの価格相談・決定
制作費の相談・決定(商品の制作者への支払い)
![]()
9月6~13日
生地の買い付け・現地を実際に訪れて学ぶ・写真や映像の影のために
ホワイフンタイ村でスタディーツアーのホームステイを行う
![]()
9月中旬
被災地へ発送
加工スタート
![]()
10月18~20日
紅陵祭での販売
他イベントやネットでの販売
紅陵祭での販売後にパティオでの販売を交渉する
![]()
11月初旬
ワークショップ
![]()
12月初旬
今年度の売り上げを計上する
![]()
12月初旬
次年度の計画を立てる
継続可能か否か
受け入れ先、生産数、販売方法、販売場所の再議
![]()
勉強会
・企画を実行するにあたり、週1回の勉強会を行う
・フェアトレードと経営の内容を取り入れる。基本や方法を学ぶ
・同時に企画のルール作りをする
![]()
事前研修
(買い付け、発送、製造など次の工程に入る前に行う)
・役割分担決め
・ルールの再確認
・目的意識を高める
・その他
![]()
報告書
それぞれが企画から実行までの活動に関わり得たもの、感じたことを報告書に
まとめ、視覚化して記録しておく。その後、HPや広報誌(月刊誌とは別)に
掲載し、他の人も見られるようにする
![]()
報告会
・活動を通して感じ考えたことや今後できること、学んだものを伝える
・学生の行動するための一歩を踏み出すきっかけをつくる
・南三陸・ホアイフンタイ村に興味を持ってもらい、
スタディーツアーを行えるようにする
![]()
※途上国や被災地の自立への支援は長期的に行う必要があるため、今後も継続してできるようにしたい
![]()
奨励金 130,000円
![]()
材料費
50,000円
![]()
買い付け費用
1人 12,000円支給 ×3人 = 36,000円
![]()
南三陸での打ち合わせ費用
1人2,000円支給 ×3人 = 6,000円
![]()
販売諸費用
資料・パネル作成費用 9,000円
ブースのテント・テーブルを借りる費用 10,000円×2回 = 20,000円
→紅陵祭においてのパネル・テント・テーブルは大学の貸し出しを利用する
![]()
募集説明会・募集会・
報告書作成費用
報告書作成費用 9,000円
![]()
奨励金で足りない分は自己負担。
![]()