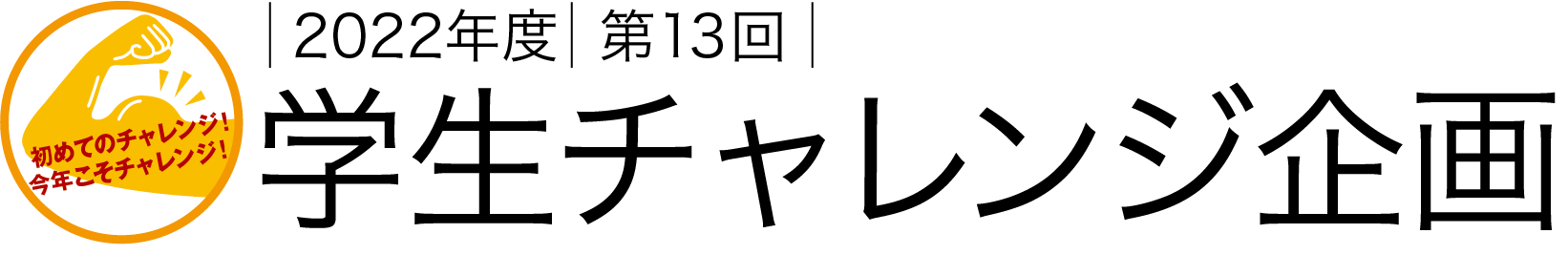拓こう!繋ごう!食の未来!
サマースクールin子ども食堂
- 団体名 拓SHOKU堂2022
- 代表者 国際学部 国際学科 3年齊藤 美空
活動記録
| 2022年5月10日~11月15日 | |
| 5月10・28日 | 子ども食堂カフェ北野で朝食ボランティア |
|---|---|
| 6月7日 | 企画打合せ、タスクチーム分け |
| 6月14日 | イベント内容の決定 |
| 6月30日 | 子ども食堂カフェ北野にて朝食ボランティアおよびイベントの打ち合わせ |
| 7月12日 | 八王子産玉ねぎの寄付(拓殖大学農園で作られたもの)。イベント準備 |
| 7月15日 | 子ども食堂カフェ北野スタッフとイベント日時決定(コロナウイルスによるイベント中止までのこの時点では、2022年8月16日・9月第2、第3土日開催予定でした) |
| 7月19日 | 再打合せ(新型コロナウイルス感染拡大により、食事を伴わないイベントに内容変更) |
| 8月13日 | 8月のイベント中止決定(9月に関しても上旬の開催が見込めない、中心メンバーの体調不良者が多かったことからメンバー同士が対面で集まりイベント準備を行うことが難しいと判断) |
| 8月20日 | メンバー同士でのZoomを利用した話し合い。2つのイベント中止に伴い、BFC※プロジェクトの開催(食育に関する配信・ハッシュタグ企画)の検討・決定 |
| 9月1日 | Zoomにて紅陵祭・10月開催予定のイベントの内容決め・話し合い |
| 9月21日 | 八王子市 由井市民センターにて、イベントのリハーサル・BFCプロジェクトのインスタライブ配信撮影 |
| 9月27日 | イベントの準備・打ち合わせ |
| 9月29日 | 道の駅 八王子滝山にてイベント用野菜購入(八王子市の農家さん:生産者 石川稔さん・関 純一さん) |
| 10月1日 | 子ども食堂カフェ北野にて食育イベント開催、食堂スタッフにインタビュー・短編ドキュメンタリー撮影 |
| 10月3日 | 短編ドキュメンタリー編集・動画完成 |
| 10月8日 | 朝日教育会議2022にて活動紹介のプレゼンテーション |
| 10月11日 | 紅陵祭準備 |
| 10月14日 | 紅陵祭にて短編ドキュメンタリー上映(視聴者数10名、アンケート回答数5名) |
| 10月25日 | BFCプロジェクト(※)認証ラベル紹介動画の撮影 |
| 11月15日 | 石川一喜ゼミナール公式Instagramにて動画配信予定 |
企画概要
八王子市にある子ども食堂カフェ北野にて、3歳~12歳の子どもたちを対象に、食への感謝・食の多様性・食の地産地消の3つのボーダーレスの理解を目的に、食育イベントを実施。中国の留学生メンバーによる大豆ミートを使用した餃子づくりを行い、食文化と大豆ミートが持つ環境問題解決の可能性を子どもたちに伝えた。これらの活動を短編ドキュメンタリーにまとめ、紅陵祭で上映。孤食などのセーフネットとしても機能する子ども食堂の存在価値についても発信した。
※BFC(Borderless Food Culture):フードロスや食の多様性理解を目的としているプロジェクト。


活動の目的と目標
1.背景
ゼミナール活動の一環で参加した八王子市にある子ども食堂カフェ北野の朝食ボランティアを通じて実感した①フードロスと②コロナ禍における異文化交流機会減少の2つの課題に向き合うプロジェクトを企画しました。

2.目的と目標
食堂スタッフの方は子どもたちが社会問題や多様性を学び、主体性や自立心の育成を望んでいます。一方、留学生が多く在籍し、かつ同市に位置する拓殖大学の学生は、日頃から社会の持続可能性を研究テーマとする学生を擁しています。本プロジェクトでは、子どもたちに食のボーダーレス化へのアプローチを考え、3歳~12歳の子どもたち(目標15名)を対象に、食への感謝・食の多様性・食の地産地消の3つを理解してもらうことを目的として、異文化交流を取り入れた食育イベントを実施。
そして活動の様子の撮影と、食堂関係者にインタビューを行い、短編ドキュメンタリーの作成とSNSにおける情報発信を行います。
食という1つのテーマをより多角的に捉え、現代社会における様々な問題や異文化理解に繋げ、活動を通じた時のボーダーレス・食のボーダーレス・生産者と消費者のボーダーレス実現によって、国境のボーダーレスの達成を目標に掲げました。

活動実績の報告
1.食育インスタライブ配信
はじめに、SNSから始める食のボーダーレス化の実現を目的として、子ども食堂イベントのリハーサルも兼ねた食育インスタライブ配信を拓殖大学の学生・他大学の学生を対象に約50分間のインスタライブを実施。視聴回数は、10月30日(日)時点で73回と多くの方が閲覧してくれました。インスタライブでは、フードロス問題について考えてもらえるよう、有用性の高い大豆ミートを使用した餃子を作ってその魅力を伝え、これからの時代の日常的な食材として取り入れてもらうことを目的に配信しました。また人参の皮を利用したチヂミのレシピも紹介。フードロス対策への具体的なアプローチも図りました。
2.子ども食堂での食育イベント
イベントでは、留学生のチームメンバーより大豆ミートを使用した中国式の餃子づくりと中国の文化を紹介しました。食の多面的なボーダーレスを実現するために、「伝え方」を工夫しました。伝え方で重要視したのは「子どもの立場に寄り添ったワークショップの運営」です。イベント前のミーティングで、「小学生の子どもたちに一方的に伝え、特に環境問題に関してずっと聞かせると彼らは飽きてしまうのではないか?」「低学年の子どもたちには難しい」という懸念が生まれました。そこで、小学生の子どもたちでも知っている情報から初めにアプローチし、クイズや中国語での会話を通して子どもたちに飽きさせない工夫を考えました。その結果、中国と日本の違いから説明するのではなく、両国の共通点から知ってもらうように投げかけ、大豆ミートに関しても子どもたちにとってのメリットを教え、説明する際はイラストを多く使用することにしました。また興味を持ってインプットとアウトプットをしてもらえるように、クイズでは「覚えられたらお菓子をプレゼント!」というアプローチの仕方に変え、楽しく学べるように心がけました。

3.アウトプット
次に私たちは、子どもイベント実施までに得た気づきや学びを、朝日新聞社と拓殖大学が共催するフォーラム「朝日教育会議」で発表しました。私たちが子どもたちへのアプローチで工夫したポイントを中心に、観覧いただく多くの方に伝え、中には私たちのプレゼンに対しての評価やフィードバックをしてくださる方もおり、非常に学びの多い機会となりました。
4.反省点
活動の反省点は主に2つあります。1つ目は、子ども食堂イベントを一度しか実施できなかったことです。8月と9月にイベントを計3回実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、やむを得ず2回のイベントを中止し10月に延期開催しました。2つ目は、子ども食堂イベント実現に向けての準備不足があったことです。新型コロナウイルスの影響に伴い、対面で集まって運営することが厳しくなり、一部のメンバーに負担が偏ってしまうような仕事配分や、子ども食堂側とのイベントの日程調整や、当日の授業の準備、紅陵祭で上映するドキュメンタリー制作などが期限間際になってしまっていました。
2回のイベント中止に対して、コロナ禍でも何かできることがないかと模索した結果「BFCプロジェクト」というものを新たに立ち上げて実施することにしました。これは、(※)ボーダーレスフードカルチャーの略で本企画のもう一つの目的であった食のボーダーレスを拓殖大学の学生間を越えて世界に発信し、実現するというものでした。こちらに関しては、実施中で「食で変えられる環境問題や社会問題、認証ラベルについて」動画で配信予定です。動画配信は、これまで関わりが少なかったメンバーにも携わってもらい、2つの反省点の改善に向けて動き出しています。

活動成果
先述の通り、子ども食堂でのイベントは1回きりとなりましたが、イベントには12名の子どもたちが参加してくれました。集客面での目標達成はできませんでしたが、餃子作りを楽しんでもらうことができました。環境問題や中国語に関するクイズも多くの子どもたちが正解し、留学生とも仲良くなっていた様子を見ると、国境のボーダーレス、時のボーダーレスは実現できたと思います。クイズでは子どもたちが自主的に手を挙げて発言していて、主体性、自立性を促すことに貢献できたのではないかと考えており、社会人基礎力の「働きかけ力」は特に身につきました。しかし、3つ目の消費者と生産者のボーダーレスを目的とした活動に関しては、八王子産の玉ねぎの寄付や道の駅八王子滝山で販売されていた八王子市の生産者が作られた野菜も使用したものの、地産地消の背景にある環境問題や社会問題をうまく伝わるようにアプローチできなかったと感じております。
活動を通して、子どもたちは私たちが思うより、未熟ではないと感じました。子ども目線に立ったワークショップを計画しましたが、実際には大豆ミートについて沢山学んでおり、主体的に活動に取り組んでいました。スタッフの方が、「子どもたちは少し難しいことの方が興味を持って取り組むし、本来みんな学びたい!という気持ちがある」と教えてくださり、少し難しいクイズや餃子の包み方も楽しんでくれている子どもが多いことが分かりました。
中でも、スタッフの方へのインタビューで私たちの考える子ども食堂への固定観念への気づきは大きな収穫でした。子ども食堂に対して「貧困」などのイメージが連想されることがありますが、この食堂は「子どもたちの居場所」として地域交流の重要な役割を担っています。「こども食堂=貧困」と連想されることで、利用しづらい家庭が増えることもあるため、活動には十分に注意しながら発信する必要があると感じました。少ないメディアで得た情報や固定観念など、私たちの心の中には、自分では意識していなくても社会に対する見えないボーダーがあるのではないか、と確認することが大切であると思いました。

インタビュー質問内容
[これまでについて]
◎これまでにどんなイベントを実施したか。どんなイベントが子ども達に人気か。
◎活動の中で大きな変化を感じた出来事や印象に残っていること。
◎なぜ子ども食堂に携わろうと思ったのか。活動を始めたきっかけ。
◎やりがいを感じるときはどんな時か。
◎コロナ禍ではどのようなイベントを実施したか?工夫点など。
[現在について]
◎毎週どのくらいの人が子ども食堂を利用するか。どんな年齢層の人が来るか。
◎ 子ども食堂はどのような場所か。
◎今、感じている課題。
◎今、学生達に伝えたいこと。
[これからについて]
◎どんな社会になったらいいと思うか?
◎子ども食堂の今後の展望や目標
インタビューキーワード
◎子ども食堂=貧困ではない。
◎心へのアプローチ、心に幸せを届ける。
◎コロナの現状よりも心の健康のほうが深刻な問題。
◎子どもを“地域で”育てたい。地域の役割の重要性。
◎本来子ども達は学びたいという意欲が誰にでもある。
◎成績や勉強で判断されない価値観の多様性を提供する。
◎学力以外の物差しを作る。
◎子どもは簡単なものよりも、少し難しいものに関心がある。
◎発展よりも継続することの重要性。
◎大学生の役割 子どもに対し、違う価値観を与えられる。


会計報告
- 活動資金 27,610円
- 支出総額 26,711円
| 項 目 | 小 計 | |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 子ども食堂カフェ北野交通費 | 4,230円 |
| 子ども食堂イベントレシピ 授業資料印刷費 | 480円 | |
| イベント消耗品費 | 1,870円 | |
| 紅陵祭ブース用消耗品費 | 440円 | |
| リハーサル・イベント当日食品 | 7,149円 | |
| リハーサル用キッチンスペースレンタル | 2,000円 | |
| 認証ラベル動画作成用 食品代 | 10,542円 | |
| 合 計 | 26,711円 | |
- 活動資金 154,000円
- 支出総額 127,204円
| 項 目 | 子ども食堂カフェ北野交通費 | 小 計 | 4,230円 |
|---|---|---|---|
| 項 目 | 子ども食堂イベントレシピ 授業資料印刷費 | 小 計 | 480円 |
| 項 目 | イベント消耗品費 | 小 計 | 1,870円 |
| 項 目 | 紅陵祭ブース用消耗品費 | 小 計 | 440円 |
| 項 目 | リハーサル・イベント当日食品 | 小 計 | 7,149円 |
| 項 目 | リハーサル用キッチンスペースレンタル | 小 計 | 2,000円 |
| 項 目 | 認証ラベル動画作成用 食品代 | 小 計 | 10,542円 |
| 合 計 | 26,711円 |