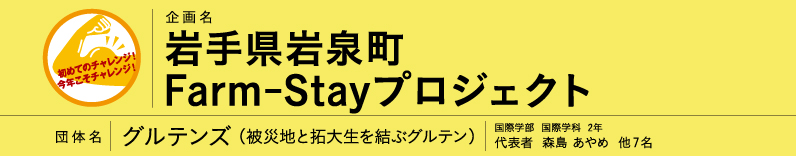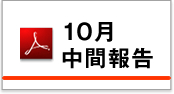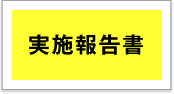2013年度(第4回)学生チャレンジ企画 実施報告書
実施内容 成果 反省点・今後の展望 収支報告 ホームページ掲載
実施内容
実施スケジュール平成24年11月17日~平成25年11月4日
| 11/17 | 岩手県岩泉町訪問、 同町議会議員坂本昇氏と協議 |
|---|---|
| H25 3/ 9 | 同町農家と「ファームステイ プロジェクト」基本合意 |
| 6/14 | 同町町長表敬訪問とファームステイ 農家訪問 |
| 7/2 | 坂本町議会議員と打ち合わせ |
| 7中旬 | 企画最終確認、参加者打ち合わせ (事前研修) |
|---|---|
| 7/29~9/15 | ファームステイプロジェクト の実施 |
| 11/1~3 | 坂本氏、ファームステイ農家へ 御礼挨拶、評価、反省会 |
| 11/4 | 参加者報告会 |
その後数回のメール連絡を経て6月14日、同町の町長へ表敬訪問しました。
 8/5 岩手県岩泉町にて、佐藤椎菜(一番左)三瓶由香里(左から二番目)、受け入れ農家
8/5 岩手県岩泉町にて、佐藤椎菜(一番左)三瓶由香里(左から二番目)、受け入れ農家
さんと記念撮影
 8/1 岩手県岩泉町にて、佐藤優介、
8/1 岩手県岩泉町にて、佐藤優介、
草刈り作業
ファームステイの趣旨などの説明をし、理解をいただきました。
同時に農家訪問。趣旨説明をし、快諾をもらいました。
7月2日、坂本氏と、参加者の希望農家とのすり合わせなど、具体的な打ち合わせをし、7月中旬にかけて
坂本氏との企画の最終確認をしました。
予定では同町を訪問予定でしたが双方の日程が合わず、電話により最終打ち合わせとなりました。
その後国際学部棟内にて参加者との事前研修。7月29日よりファームステイプログラムの実施しました。
以下、実施期間と参加者氏名、所属学部、学年、体験農家の業種です。
◎7/29~8/4 佐藤優介(国際1年) 酪農
◎8/2~6 土屋琴美(国際1年)、
八町まなみ(国際1年) 畑作
◎8/5~11 佐藤椎菜(国際1年)、
三瓶由香里(国際1年) わさび
◎8/5~11 鈴木詩織(国際1年) 酪農
◎8/25~29 中村早穂(国際2年) わさび
◎9/3~7 酒井園香(国際2年) 酪農
◎9/3~8 西條那奈(国際1年)、
小澤波乃(国際1年) わさび
◎9/10~15 大谷美倭(国際1年) 酪農
酪農では牛舎の掃除、牛の餌やりなど、牛の世話を中心に体験。
わさび農家ではわさびの洗浄、加工、出荷作業を体験。
畑作農家ではピーマンの収穫、量り、袋詰めなどの出荷作業を体験。
ほかにも坂本氏のご厚意で岩手県各所の視察などもさせていただきました。
11月1~3日にかけて再び岩泉訪問、坂本氏とファームステイ農家へ御礼。坂本氏から今回のファームステイプロジェクトの評価をいただき反省会を行いました。
11月4日には参加者の報告会と振り返り、評価をもらいました。
 8/4 岩手県岩泉町にて、土屋琴美(左)
8/4 岩手県岩泉町にて、土屋琴美(左)
八町まなみ(右)、ピーマンの量り、袋詰め
作業
 8/10 岩手県岩泉町にて、鈴木詩織、牛舎の掃除
8/10 岩手県岩泉町にて、鈴木詩織、牛舎の掃除
 9/5 岩手県岩泉町にて、西條那奈(左)
9/5 岩手県岩泉町にて、西條那奈(左)
小澤波乃(右)、わさびの洗浄作業
成果
岩泉町の方に対して
過疎化が進む岩泉町にとって、若い学生がこの町にやってくること自体が珍しく、この町にとっては大変喜ばしいことだそうです。昨年の夏に訪問した第一回ファームステイ企画において岩泉町に住む方々からは、「生きる希望をもらった」という声や、過疎化に伴い厳しい人手不足に悩まされていた農家の方々からは「手伝ってくれて助かった。おかげで出荷に間に合った」という言葉をいただきました。今回の企画で現地と私たちのパイプ役になってくださった坂本氏からは「岩泉を知り、来てくれただけでもありがたい」とおっしゃっていました。微力ではあるかもしれないが、目に見える部分ではもちろん、見えない部分でも私たち学生が岩泉の方々の力になれたなら、それは成果として実を結んだと思います。
私たち学生に対して
普段土を触らない人や虫が苦手な人、野菜が苦手な人など、今回の参加者の中にはこういった学生がたくさんいました。しかしファームステイに参加し、農家の手伝いや、大自然に囲まれた生活を送っている中で自然と克服して帰ってきた学生が多くいました。参加を終えた学生の話を聞くとどの学生も成長して帰ってきたと、岩泉で学び得たことで将来に大きく役立つことがあったと報告がありました。なかには農家になりたいという学生もいました。朝起きて太陽に感謝したり、畑で汗をかいて食べることに感謝をしたり、夜は満点の星空を見ながら眠りにつく。そういった自然の中の生活は、時に自分自身を大きく成長させるのだと感じさせられ、また、大自然から学ぶ事はまだたくさんあると強く確信しました。農業の知識を得て、過疎化の地域の現状を知り、大自然のなかでひと夏を過ごし、自分自身と向き合ったり、将来をみつめたり。私たち学生にとっても良い影響を受けた企画となりました。
反省点・今後の展望
今回のファームステイプロジェクトの最大の反省点は、私たち代表が、参加者の体調管理をしっかりできなかったことです。私たち代表が岩手県岩泉町へ訪問したのが冬から春先だったので夏の岩泉の気温を把握することができませんでした。実際は想像と異なり朝と夜が冷えたらしく、参加者にそのことを伝えていなかったので参加者の体調管理がしっかりできませんでした。また、坂本氏との連絡もそこまで及んでいなかったので、参加者には不便をかけてしまいました。
その他にも、坂本氏との間で連絡の行き違いやタイムラグがあり、坂本氏と農家の方との間の連絡も遅くなってしまった。岩手県はすぐに行ける距離ではないので連絡手段が限られてしまっていたこと、顔を合わせて会議をすることがあまりできなかったこともあり、プロジェクトを円滑に進めることができませんでした。また、参加者と坂本氏と私たち代表との間でも連絡に行き違いがあり、参加者には不安を残したまま岩泉へ行かせてしまいました。
取決めの部分でも不十分な部分があり、宿泊料は払うべきなのか、給料はもらって良いのか、など徹底できていませんでした。
不十分なことが多々あり、参加者には不満もあったと思うのにもかかわらず、来年もあったらまた参加したい。岩泉へまた行きたい。大学では体験できないようなことが体験できました。名残惜しい、などという声が参加者全員から聞かれ、このプロジェクトをやった意味があったと感じました。そもそもこのプロジェクトの目的は、東日本大震災によって若者の過疎が著しくなった岩手県岩泉町を学生に知ってもらい、実際に足をはこび、岩泉を好きになってもらうことと、農業を通じて被災地と拓大生を結ぶこと、ファームステイを通じて農家さんには人材と地域活性を、拓大生には農業知識と技術習得という双方のメリットを目的としていたので、きっかけとしてそれは達成できたと思います。
次回以降の活動については、これらの反省などを含め、取決めなどをしっかりと決め、ファームステイモデルの確立を目指し、安定したプロジェクトの運営とより多くの学生に参加してもらえることを目標とします。また、この岩手県岩泉町のプロジェクトが確立した後には、これを国際学部がある八王子市や北海道短期大学のある深川市へも拡大し、本格的なファームステイの定着を目指します。
収支報告
| 支出総額 544,880円 | 奨励金 180,000円 |
内訳
| 項目 | 小計 |
|---|---|
| <交通費> | |
| 東京-盛岡 10,000円 | |
| 盛岡-宮古 3,940円 | |
| 宮古-小本 15,000円 | 347,280円 |
| <民泊費、食費> | |
| 滞在一週間の場合 一食300円×3×7×12 | 75,600円 |
| 項目 | 小計 |
|---|---|
| <謝礼金> | |
| 一農家 10,000×12 | 120,000円 |
| <広告費> | |
| ポスター作成費 | 1,000円 |
| 報告書印刷費 | 1,000円 |
※ 奨励金は広告費、交通費、謝礼金にそれぞれ負担 合計 544,880円
Copyrights (C) 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.